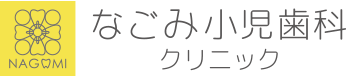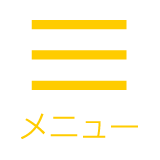ブログ
「ホワイトニング」を子供はできない!?歯科医院でのクリーニングとフッ素塗布がおすすめ
2020年10月20日
白い歯は魅力的です。
薬剤を自宅で塗ってホワイトニングをする大人は多く、お子さんにも同様のサービスを受けさせたいとあなたは思っているところかもしれません。
しかし子供向けにホワイトニングのサービスをしている小児歯科医院などが近くにないのではないでしょうか。
なぜ子供向けにホワイトニングを行う歯科医院が少ないのか、また行なっている歯科医院ではどういった施術が行われているのか。
子供のホワイトニングについて情報をまとめてみます。
(さらに…)
歯並びや舌小帯短縮症など!!遺伝するかもしれない口周りのトラブル
2020年9月22日
あなたは虫歯や歯並びで小さい頃に困った経験はありますか?
口周りのトラブルの中には遺伝の可能性が指摘されているものがあり、あなたに症状があればお子さんにも遺伝する場合があります。
どんな症状や病気に注意した方がいいのかをまとめて紹介します。
(さらに…)
「離乳食」は生後5〜6ヶ月ごろから!作り方や進め方の注意まとめ
2020年8月18日
お子さんは「指しゃぶり」や「オモチャなめ」をしていませんか?
そろそろ「離乳食」の練習を始めてもいい時期かもしれません。
母乳や育児用ミルクから固形物への切り替えはお子さんにとって大きな挑戦です。
歯の生え方や成長には個人差があるのを十分に理解しつつ、今回紹介するような点を注意して離乳食の練習を始めましょう。
(さらに…)
「舌小帯短縮症」の手術は保険適用!MFTトレーニングも小児歯科で
2020年6月23日
あなたのお子さんは上手に哺乳をできていますか?
少し大きなお子さんの場合は発音やアイスクリームの食べ方をチェックしてみましょう。
なかには「舌小帯短縮症(ぜっしょうたいたんしゅくしょう)」で舌がうまく使えていないお子さんがいるかもしれません。
状態がひどい場合は手術やトレーニングが必要になります。
舌小帯短縮症の症状や処置についてまとめてみましょう。
(さらに…)
歯垢と舌苔の除去がカギ!?感染症の予防効果が期待できる口腔ケア
2020年5月12日
新型コロナウイルス(病名:COVID-19/ウイルス名: SARS-CoV-2)が世界中で感染拡大しています。
あなたも感染予防を心がけて手洗いやマスクの着用を実践されていることでしょう。
ウィルスや細菌の感染予防に口腔ケアが役立つとの結果が日本やアメリカの研究で出ているのをご存知でしょうか。
口腔ケアが感染症予防につながる理由や自宅で行う際のポイントをまとめて紹介します。
(さらに…)
「萌出嚢胞」とは!? 子どもの歯茎に黒紫の水ぶくれができたら!?
2020年4月21日
お子さんの口のなかを注意して見ていますか?
歯磨きで毎日見ているからと気を抜いていたら、歯茎が黒紫色に腫れてビックリ!!
それは「萌出嚢胞」と呼ばれる症状かもしれません。
見た目が痛々しく腫れてしまうと驚かれる親御さんも多いでしょう。
どのような症状でどのような処置が必要なのか、まとめて紹介していきます。
(さらに…)
赤ちゃんの歯が生える前兆4選!!よだれ・夜泣きが増える⁉︎
2020年3月30日
赤ちゃんの歯は一般的に生後6〜9ヵ月頃に生え始めます。
しかし、歯が生え始める際に様々な兆候が見られるのをご存知でしょうか。
あなたが無関係に思っている行動や症状も、実は歯が生えてくる前兆かもしれません。
歯が生えてくる前兆と知らず、違った対応をしてしまったらお子さんの負担になってしまう可能性もあるでしょう。
今回は歯が生えてくる前兆として知っておきたい4つをピックアップしました。
生後6〜9ヵ月頃の赤ちゃんをもつ親御さんは、当てはまるところがないかチェックして見てください。
「抜歯」は歯科医院でやるのが基本!こんなとき家で抜いてはダメ!?
2020年3月17日
乳歯がグラグラしている。
あなたも身に覚えがあるかもしれませんが、6〜7歳ごろに乳歯から永久歯へと歯は生え変わります。
お子さんの歯も自然に抜けて生え変わればいいのですが、小児歯科などで診察・処置が必要な場合があるのです。
抜歯をしなければならない原因や、どういった場合に病院へ行った方がいいのか、さらに自宅でもし抜くときにはどのような点を注意したらいいのかをまとめて紹介していきます。
(さらに…)
鬼歯・魔歯!リガフェーデ病にもつながる「先天歯」の対策
2020年2月18日
生まれたてなのに歯が生えている!?
授乳中に乳首が痛むと思ったら生後ひと月程度なのに歯が生えていた!?……と驚かれた人もいるでしょう。
このように歯が生えて赤ちゃんが生まれてくるケースや予定よりも早く歯が生えてしまうケースがあるのです。
原因は特定されていないのですが、なかにはすぐにでも小児歯科に相談して処置した方がいい場合もあります。
それがどういった場合なのか・またどういった処置をするのかをまとめて紹介します。
これが原因!子どもの「歯ぎしり」自宅でできる3つの対処法
2020年2月14日
お子さんの「歯ぎしり」が気になった経験はないでしょうか?
歯ぎしりをする子どもは少なくなく、実は原因もちがうのです。
子どもの歯ぎしりの原因3つと、
それぞれどのような対処をすればよいのかをまとめました。
お子さんの歯ぎしりの様子と照らし合わせてみてください。